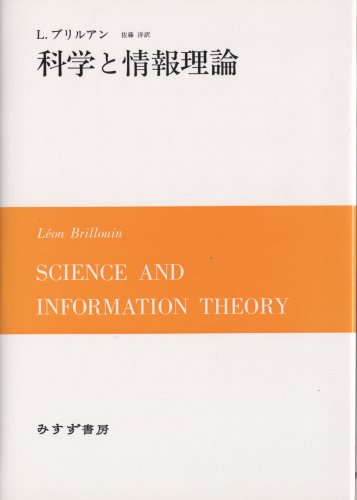存在論について早くから緻密な思考をめぐらしていた古代インド人は無をカテゴリ論の一部として扱う。それを行ったのは後代のヴァイシェーシカ学派だという。無を非存在と同義として、この学派は無を4種にわけた。
未生無、乙滅無、畢竟無、交互無
未生無は心のなかでの観念としての無、乙滅無は滅失した後の非存在、畢竟無はある場所に過去現在未来にわたっての存在がないことだ。交互無はAとBという事物が別々あるならば、AにあってはBは不在とする。事物の差異はこの交互無から生まれる!
空と無は何が違うのだろう?
空は中がうつろである。サンスクリットのsunyaは膨れ上がったものを指していた。膨れたものは中がうつろである。記号「0」もそれを形象化している。
無はasatとして空とは区別されている。有の反対語であろう。空ですらないことだ。
論じる対象すらないことが無なのだ。それに対して「空」は至るところにあり、すべてに含まれ、すべてを含んでいるのかもしれない。
ところで、因明と呼ばれるインド論理学では否定としての「無」を扱うだろうか?
ja.wikipedia.org
閑話休題。
数学とのアナロジーを考える。空集合は確かに「空」である。集合{ } の中身はないからだ。その要素の数は「0」だ。集合とは共通要素をもつ、あるいは概念の当てはまる対象を区分けすることだろう。
あきらかに無とは違う。数学ですら無は扱えないとみるべきなのだろうか?
「ゼロ」の起源から考えよう。
「零の発見」という吉田洋一の名著があったが、ゼロはインド人たちの発見である。インド思想での「空」との類縁性は疑えない。発想の根元は同じだろう。存在論の概念が数学に持ち込まれるというのがユニークだ。同じくゼロ記号を持っていたマヤ文明ではどんな理念からゼロが持ち込まれたのだろう?インドほど文献が残っていないためそれを再現するのは不可能なのだろう。
サンスクリット語のSunya=空は中東(アラビア)経由で西洋に入ってゆく。
中村元は指摘している。
「0」の記号は、もとはサンスクリットのゼロをあらわす記号に由来するもので、非常によく似ております。
吉田洋一の本にその変遷を示した図がある。

開集合はその点で興味深い。幾何的視点での開集合には境界がない。無境界だ。
直接扱えない対象、近傍から接近することはできても、そこにはたどり着けない。
それが数学における「無」の扱いなのではないかと思うのだ。無限小や無限も同じ扱いのようだ。
0は操作可能だが、無は操作の埒外にあるといえば伝わるかなあ。この御託は学者先生がどうその差異を論じているか見つけていないので、あくまで私見になる。
それゆえに、下のwikiの無の記述と自分の解釈は異なっているわけだ。数学では零は空に相当し、無は直接扱っていないのだと思う。ある種の極限概念として彼方にある。
無のかわりにその逆の無限大∞を扱うのだが、これは無ではないが無の双対だ、と思う。リーマン球面からZero点が無限遠と対応づけることから、勝手に双対だといっているだけなのだが、自分は妙に腑に落ちる。
ja.wikipedia.org
数学の兄弟分のコンピュータ科学では0とNULL(ヌル:ドイツ語のゼロ)を区別しているが、前者は「空」であり、後者は「無」に対比できるといえる。計算機での取り扱い範囲外が「無」だろう。NULLは「非」とも訳されるが、観念論の国のドイツからの移入であるのが絶妙ではないか。
自然界を対象にする自然科学、とくに物理学も数学に掣肘されているようだ。
熱力学第三法則 絶対零度には到達できない。ゼロ点振動、カシミール力などは空→ゼロの観念上の扱いになるだろう。対創生も「空」からの素粒子生成を連想させる事象だ。
科学史での「空」の認識での一大事件は「真空」の発見だった。英語ではvacuum,voidになる。これはトリチェリの実験やマクデブルクの半球といった真空の存在=大気圧の証明につかわれた実験器具を思い浮かべれば「空」という訳語は正しい。
当時支配的なスコラ的自然学はアリストテレスの系統をひくものだったが、真空への恐怖 horror vacuiにおびえていた。どうやら、原子論や唯物論への根っからの反感があったからではないか。
完全なる空を認めることはキリスト教神学への反逆であり、無神論につながるとみていたからではないか?
空があることが無神論になるという思考回路はなかなかに深いのだが、どうだろう。
他方、無はキリスト教神学には無縁だった。エックハルトやタイラーは別だろうが。
真空はいくたの保守的かつ神学的な反対を押し切って、西洋世界で確立された。ニュートン力学誕生前夜の出来事だった。
空の代表的等価物である真空が宇宙空間を占有することはニュートンがその天体への力学応用で実証されてゆく。
自然科学では空についての長い歴史があったわけだ。
よって、自然科学は空を対象にすることは可能だが、無は除外しているとひとまず断定しておく。無とは本来、非存在だからだ。自然科学はなんらかのレベルか意味で存在していないものをいくら踏ん張っても研究対象にできないのだから。
つまるところ、無を考察できるのは、形而上学か宗教かのいずれかであろう。
無と空は異なる。空は自然科学の諸学諸賢が考究してきた。それに引き換え、無は無視されているようだ。でも、自分にとっては無は考察するのに値する対象だと思う。
なんといっても、無は言語表現を超え、あるかないかについて人智ではとらえどころがなく、それでも超越論的な光芒を放って堂々巡りとなりうる思考をおびき寄せるものがある。
タイトルは「無の物理学」とあるが、空の物理学を論じているのだ。ただ、原題はvoidなので、空の物理学なのだが。
インド人は空想力に長けた民族と富永仲基は指摘したが、果てしなくロジカルであることも忘れてはならない!